供養について|愛知県小牧市のお寺「薬王寺」
メールでのお問い合わせ
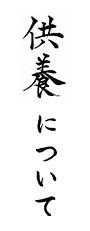

弔うということ
- 弔いはあなたの為の
大切なこころの区切り - 「弔う」本来の意味を知っていますか?
弔いは、ご先祖や亡くなった方に感謝と想いを寄せる大切な行為であり、故人への祈りであると共に、遺された者にとっても必要な時間です。葬儀や法要、お墓参りは「しないといけないこと」ではなく、「したいこと」であるべきだと思っています。
私たちはあまりに忙しく過ぎていく日々の中で、失くしたものを振り返る時間もありません。だからこそ、時代に合った方法で、あなたが続けられる供養を薬王寺でご案内します。
遺された者の
心の整理
大切な方を
近くに感じる
かけがえのない時間を
大切に想う
- あなたに合った方法で、
無理なく続けられる供養をしませんか? - ずっとこの先も、大切な人と共に
永代供養

- ご遺族と共に
お寺が供養いたします - 現代のニーズに合ったお墓のカタチ。「様々な理由でお墓の管理が難しい」「先祖のお墓じまいを考えている」また「今は良くても将来的に不安を感じている」という方が増えています。無理なくあなたに合った方法で「続けられる供養」を一緒に行いましょう。
永きに亘って捧げる
大切な方への供養
家族だけの個人墓
ご一緒に供養を行う合祀墓
法要・葬儀

- 先立たれた方を偲び、
また会う日を楽しみに - 薬王寺では、枕経からお通夜、葬儀、また法要においても、亡き人との大切な思い出が蘇るよう、ご遺族の皆さまに寄り添った供養をいたします。また、ご縁があれば全国各地へもお伺いさせていただきます。
こころを込めて執り行います
あの人へ想い届くように
ご親族での
食事の用意も完備
法要・葬儀
全国各地へも伺います
よくあるご質問
- Q.そもそも供養って?
何でやらないといけないのですか? - A.供養の本来の意味は、「お供物をして、ご先祖や亡くなった方に感謝し、想いを届ける行為」です。元々、仏様や神様へ感謝と尊敬の気持ちを込めてお供えをしていたことと、日本古来のご先祖への祖霊信仰とが混じり合い、現在の供養の形となりました。亡き人のご冥福を祈り、遺された者の心の整理の為にも供養することがとても大切です。
- Q.供養はどうやってするのですか?
どれくらいの頻度でどこでするべき? - A.いつでも、どこでも、供養はできます。お寺やお墓でお坊さんにお経を読んでもらい、お焼香することはもちろん供養ですが、亡き人やご先祖に対し手を合わせ、そのご冥福を祈る行為そのものが供養と言えます。日々の生活の中で取り入れると、今生きていることへの感謝が生まれ、より一日一日を大切にお過ごしいただけるはずです。
- Q.永代供養って何ですか?
- A.お寺がご遺族と共に供養を行うことです。様々な都合でお墓の管理が難しくなってしまった方に勧めたい、お寺がご遺族の方とご一緒に供養ができる方法です。
- Q.お墓の管理が難しい・・。
墓じまいするべきですか? - A.どんな方法でも、供養できる方法を見つけることが大切です。現代は核家族化であらゆるご家庭があります。本来はご家族のお墓を所有し、墓参りや法要をしっかりと行うことが大切ですが、最も大切なことは「無理なくずっと続けられる供養」です。時代と個々の生活に合った供養を一緒に探しましょう。まずはお寺までご相談ください。
メールでのお問い合わせ
- Q.お墓を考えているのですが、お寺と宗派が違うのですが大丈夫ですか?
- A.入口としては、宗教、宗派問いません。薬王寺では、入口として宗教、宗派問わずご相談を受け付けておりますが、浄土宗に沿った供養を行い、ゆくゆくは浄土宗の檀信徒としてお墓をお持ちいただければと思います。
メールでのお問い合わせ
- Q.葬儀はどこでやるべきですか?
- A.寺院、斎場でも、皆様が集まりやすい場所で構いません。お寺での葬儀は、お飾りなどが揃っているので用意する必要がないこと、住職が付き添い、故人とご遺族に寄り添った葬儀を行うことができ、斎場ですとほとんどの段取りなどを会場のスタッフが準備・進行してくれます。双方に良し悪しがあるので、ご遺族、そしてご友人が集まりやすい場所で行うことが大切です。
- Q.法要はどんな頻度で行えばいいのですか?
- A.特に決まっていませんが、初七日〜三十三回忌まで、通算15回が一般的とされています。基本的に、法要は四十九日までの忌日法要と、年単位で行われる年忌法要とに別れます。忌日法要は初七日〜四十九日までを7日単位で行い、その後一周忌、三回忌、七回忌、十三回忌、十七回忌、二十三回忌、二十七回忌、三十三回忌までが一般的ですが、ご親族が集まれる時に行うことが最も大切です。
- Q.浄土宗って何ですか?
- A.法然上人が説いた「念仏を唱えれば救われる」というみ教えです。修行を行い、覚りをひらいた者のみが救われるとされていた貴族向けの教えが主流だった時代に、「念仏を唱えれば、罪を犯した者も赦され、極楽へ往生できる」と法然上人は説き、不完全な者、貧しい者をも救われました。
- 月影の
- いたらぬ里は
- なけれども
- ながむる人の
- こころにぞすむ
法然上人(浄土宗開祖)
月の光のとどかぬ人里はないけれども、眺める人の心にこそすみわたります
